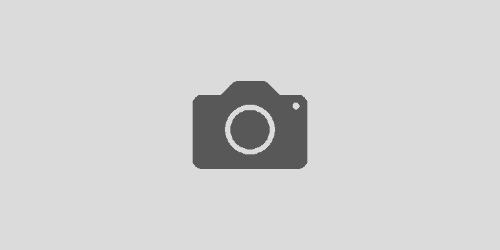「富士桜自然墓地公園」直行バス体験記

どうせ個人のブログなのだから、たまには「超ニッチ」な話題もよかろうと思い、墓地公園直行バス(往復)の利用体験記を書いてみる。
関心のある方々の参考になれば幸いだが、筆者らしく紀行ふうに、そして余計な参考情報も盛り沢山でいってみたい。
INDEX
- 富士桜自然墓地公園とはなにか
- 東京・横浜・名古屋から直行
- 横浜駅から徒歩で集合場所へ
- バスは3台
- 新東名で墓地公園へ
- 墓地公園内にて
- 死んだらどうなる?墓と葬送の問題
- ビールと冷やしおろしそばをかき込む
- 関連リンク
富士桜自然墓地公園とはなにか
「富士桜自然墓地公園」と聞いてピンとくる人には、大きく2種類あるのではないだろうか。
ひとつは桜や富士山が好きな人たちだ。そして写真撮影に凝っている人も多いに違いない。そういう人たちにとってこの墓地公園は、壮大な富士を背景にしながら、人工構造物が写り込まない桜を撮影することのできる名所である。
もうひとつは創価学会関係の人々である。正式な施設名称にあるとおり、この墓地公園の運営は、宗教法人である創価学会(以下「学会」)が行っている。
とはいえ学会関係者でないと入場禁止であるとか、入園料のようなものが必要だとかいったことはない。
だからこそ、純粋に富士山や桜を愛でたい、美しく撮影したいという人々にも支持を得ているのだろう。
この墓地にまったく縁のない人でも、墓地という場所の尊厳を守り、墓地公園の秩序・ルールを守って行動するのであれば、特に叱られるということはないようだ。
敷地面積は122万平方メートル、37万坪。
これは東京ドーム26個分、あるいは東京ディズニーランドと東京ディズニーシーを合わせたほどの広大な面積だ。
そこに染井吉野、富士桜、八重桜など約8,000本の桜が植えられている。
さて、平成以降と言っていいだろうか。お墓については様々な問題が噴きあがっている。それはつまり、墓地という施設そのものに関すること、そして葬送のあり方に関する問題だ。
これに対する様々な取り組みは、おもに民間を中心に行われており、行政は「解釈」で追認しているような状況とも言える。
究極的には、われわれ日本人の「死生観」と「家制度へのこだわり」の問題なのだろうと考えている。
東京・横浜・名古屋から直行
まず、この墓地公園へのアクセスだが、筆者はこれまで新幹線で新富士駅まで移動し、そこでレンタカーに乗り換えていた。この新富士駅からは、いちおう路線バスもあるようだが、「便利」とは言い難い。
そんなおり知ったのが、東京・横浜・名古屋からの直行バスである。
筆者は横浜在住なのだが、大人往復8,000円だ(東京発8,700円、名古屋発8,500円、いずれも2025年度)。
仮に、新横浜駅から新富士駅までを新幹線で往復すると、自由席でもザっと9,000円。これにレンタカー代とその保険料、燃料費が乗ってくる。そもそも新横浜駅というのは横浜駅からけっこう離れており、筆者にとっては不便な駅である。
人それぞれで事情は異なるけれど、筆者の場合、横浜駅からの直行バスは、じゅうぶん選択肢に入ってくる。
なお、このバス往復は「募集型企画旅行」と呼ばれる種類の、旅行会社のバスツアーに参加するということになる。
そして「最少催行人数」が設定されている旅行商品であるため、申し込み者数によっては催行されないこともあり得る。
筆者は今回、9月23日の秋分の日に参加しており、最初から「催行確定日」となっていた。
横浜駅から徒歩で集合場所へ

2025年9月23日、横浜駅で電車を降り「きた東口A」を目指す。
ちょっと奇妙な出口の名称だが、横浜駅はJRのほか、東急、京急、相鉄(そうてつ)、横浜市交通局(地下鉄)、そして「みなとみらい線」を運行する横浜高速鉄道という、合計6社局の路線が乗り入れる巨大ターミナルである。
そのため駅の出入口も多数ある。「きた東口A」は、つまり「北側通路にある東側のA出口」を示している。
集合場所は、この「きた東口A」から徒歩数分のところであり、そごうデパートの1階にある通常の路線バス高速バス乗り場とは異なる(詳細は旅行会社から事前に案内がある)。
駅からの徒歩ルートには、ほぼ屋根がある。高低差についてはエレベーターやエスカレーター、スロープがある。

集合時間は8時15分。
筆者は待ち合わせなどの際、いつも十分な余裕をもって近くに到着しておき、カフェなどでのんびり過ごすようにしている。
今回は駅で立ち食いそばでも食べて行こうと考えていたが、祝日の朝7時過ぎでは、駅構内のそばチェーンも開店準備すら始まっていない。
さらに横浜駅東口というのは大手企業のオフィスビルなどが立ち並ぶ先進的なビル街であり、とても「だし香る立ち食いそば」があるような雰囲気ではない。

どうしたものかと考えながら集合場所へ向かう。
すると「横浜ベイクォーター」と呼ばれるビルの2階に「M(マクドナルド)」の看板が灯っているのを発見、ホッとする。あさ7時から開店しているようだ。 ここなら集合場所まで、徒歩1分以内である。
「セットもの」を頼み、秋めいてきた風を感じようと、店外のテラス席に腰を下ろす。

関東地方は数日前から猛暑が和らぎ、今朝はわりと涼しい風が海の方から吹いてきている。青い空にはひつじ雲がゆっくり流れている。
ちなみにこのテラス席だけはペット同伴でもOKである。ビル2階の屋外デッキでもあり、犬の散歩をする人もよく通りかかる(さすがに、ひつじを連れている人は見かけない)。

祝日朝のマクドナルドに客は少なく快適だ。気づくと近くのテーブルには黒っぽい服を着た家族連れが座っている。
聞こえてくる会話の中にもそれらしい言葉が出てくるので、あぁ墓地公園行バスを待っているのだなとわかる。

ぼつぼつ時間なのでトイレに行っておこう。バスにはトイレがないそうだ(往路は足柄SA、復路は海老名SAでの休憩あり)。
さっきまで閉まっていたビルのシャッターが開いており、そこから駐車場を通ってフロアに入ると、トイレや自販機がある。
バスは3台
集合場所といっても、つまり広めの歩道である。そこへ路駐の乗用車を避けるようにして、神奈中観光の大型観光バスが3台やって来てとまる。
1か月ほど前に電話で予約した際、係の人は「秋分の日はもう、2台目のバスが設定されております」と言っていたが、さらに参加者が増えたようだ。
それに引き換え前後の催行予定日は、0~数名という状況で、催行中止になるかもしれないと話していた。少なくともその時点では、日によって参加者数に極端な偏りがあるようだった。
係の女性が一人、客たちの確認をしている。
座席は決まっており、筆者は1号車の中ほど窓側である。というかどうやら1号車は1名参加の人だけになっているようで、その19名全員が二人掛けシートを使用できるようアレンジされている(シート配列はごく一般的なパターン)。
さっきの家族連れは2号車か3号車だろう。
見渡すと客の平均年齢は、ザっと「65歳over」。家族に支えられながら歩く人も少なくない。どうやら骨壺が入っているらしい立方体のリュックを担いでいる男性もいる。
そういえば、人が亡くなって火葬した際、遺骨のすべてを骨壺に入れる地方と、そうではない地方が、西日本と東日本で別れるのだとか聞いたことがある。
バスに乗り込もうとすると、狭い通路を行ったり来たりしている人が少なくない。見ると、乗降口に貼ってある座席案内と、荷棚に表示されている座席番号が符合させにくい。
団体、とくに高齢の団体を効率よく捌くためには、こんなちょっとした部分のセンスが問われる。
新東名で墓地公園へ
秋晴れと言ってもいい空の下、バスは首都高速神奈川1号横羽線、3号狩場線、保土ヶ谷バイパスを経由して、まずは横浜町田ICから東名高速道路に乗る。
このICの西には、相模川を挟んで手前にある海老名JCT(圏央道と連絡)と、向こう側の厚木IC(小田原厚木道路へ分岐)が、わずか1.5kmほどで連続するため、このあたりはどうしても渋滞しがちである。
それでも6kmほどの渋滞を抜けたあとは、順調に走っている。
久しぶりの長距離バスは、なんだか旅行気分である。車内も静かでよろしい。
各席にはUSB充電ポートも備えられている。車内Wi-Fiもサービスされているが、一般的な無料Wi-Fiと同じく、暗号化はされていない。
東名高速で箱根カルデラの北側を、JR御殿場線と並ぶようにして回り込み、「足柄SA」に入る。ここで約20分の休憩である。
いったいサービスエリアというところに来ると、なぜか腹が減ってくる。五平餅や天玉そば、ソフトクリームが食べたくなる。不思議なものだ。しかし、PETボトルのお茶だけを買うことにする。
足柄SAを10時05分に出発。こんどは富士山の南側にある愛鷹山の南側を、標高100~200mあたりでぐるりと回りこみ、30分ほどで新東名の新富士ICから「一般道」へ出る。
ここからは西富士道路と呼ばれる道になっており、案内標識が緑色になっているため有料道のように見えるのだが、すでに無料開放されて久しい。
この道は富士山の裾野を走る幹線道路であり、どうしても混みやすい。45分ほどかかって富士桜自然墓地公園に到着する。
墓地公園内にて
この墓地公園は富士山の裾野に位置し、敷地は傾斜地となっている。
管理センターや売店がある入口付近は標高750mほどだが、上り坂を奥へ進むと830mほどまで登ることになる。
そんなところを、特に高齢の人たちが移動するのは大変なので、いま乗ってきたこの大型バスも、時間と場所を決めて1~2回、上りをサポートしてくれるようだ。ガイドさんの説明をしっかり聞いておく必要がある。
また墓地公園の方でも、ワンボックスワゴン車によるオンデマンド・サービスを行っている。ただしレンタカーや自家用車で来ている人は利用できない。
そもそも墓地公園内のほぼすべての道路わきには縦列駐車区画が設けられており、クルマがあるならオンデマンドバスを利用するまでもない。
管理センターでは、納骨などの手続きをする人々が書類を記入したり、窓口で説明を聞いたりしている。秋の彼岸ということもあり、礼拝堂の方では時間を決めて特別法要が行われている。
30分弱の特別法要を終えて外に出ると、風は涼しいものの、ワイシャツ1枚でもやや汗ばむ。
筆者が使用者となっている墓は「A区」。一番上の方にある区画だ。
しかしここは、自然を愛でながらのんびりと歩いて行こう。横浜への帰りのバスは午後2時に出発するから、食事をふくめても時間は十分ある。
中央分離帯と縦列駐車区画がある、この墓地公園の背骨ともいえる広い道路の歩道を、ゆっくりと登っていく。
流れるほどの汗ではないが、じっとり汗をかいている。ワイシャツのボタンを3つほど開け、手提げカバンを一つ持って登る。
この季節、もちろん沿道の桜は咲いてはいないが、それでも静かな墓地公園内をゆっくり歩くのは、空も風も清々しく感じる。
ただ、歩道を横切るようにしてクモの巣が張っていることがあり、背の高い人は気を付けた方がいい。

きょうは天気がいいものの、富士山の姿は雲に隠れて見ることが出来ない。こればかりは運ということになる。
かつて桜の時期の墓参で富士山がくっきりと見えた経験があるが、しばらく我を忘れて眺めてしまうほどの美しさであった。
墓参と簡単な掃除を終え、今度は墓地区画の中を通る歩道を、ゆっくりと下っていこう。
ときおり草のあいだに、かわいらしいキノコが生えている。しかし絶対に手を触れてはいけないようだ。立て看板によると、この周辺で猛毒のキノコが発見されているのだそうで、小さい子ども連れなどのときは注意が必要だ。
各区画はいずれも広く、同一規格の墓石が整然と並んでいる。そこに三々五々、という感じで墓参の人がいる。
地面(草地)に正座して経を唱えている(聖職者ではない一般の)人、墓石の前で亡き人に向けてヴァイオリンを弾いている人、墓石を囲んで家族写真を撮っている人、墓石に向かって一人(そこにいない)誰かとのんびり語らっている人…。
いや、「そこにいない」のではない。おそらくその人の脳内では、厳然と「存在」しているのだ。
いったい「存在」とは、他人が客観的に観測できるものだけに限らない。その人が「いる」と感じている以上は、やはり「いる」のである。
かつて「千の風になって」という歌の中で「私のお墓の前で泣かないでください そこに私はいません…」というフレーズがあった(日本語訳詞・作曲/新井満)。
「いる」とすれば、それは、そう思う人の脳内に、あるいは心に存在するということなのだろう。だからこそ空間的な特定の場所にこだわらないという考え方ができる。
とはいえ、われわれ
やはりそこでは「墓」「祭壇」「聖堂」といった物理的、空間的な場が求められることになる。そしてそこを訪れることによって、あるいは非日常に身を置くことによって、確かに精神的・心理的変化が起こり、ひいては現実世界における思考と行動に変化を生じさせることになる。
その人はいま、時空を超えて亡き人と対話をしている。
死んだらどうなる?墓と葬送の問題
最初の項で筆者は、「昨今の墓や葬送の問題の根本は、日本人の死生観と家制度へのこだわり」と書いたが、そのあたりについて私見を述べ、また参考図書などを紹介してまとめとしたい。
日本は高度成長期以後、いわゆる核家族化が進み、令和のいまでは「ひとり世帯」が全体の4割に達しようとしている(2050年にはひとり世帯が全世帯の44%となり、更にその半数が65歳以上となる見通し)。
これと同時進行するように、「一家の財産や権利、判断や責任を、長男が一手に引き受けるのが当然」「もし男子がいなければ婿養子を取る」といったような家制度の価値観は非現実的なものとなり、もはや歴史の中に出てくる価値観となっている。
しかし法律をはじめとした各種の社会制度、人々のものの考え方には、そうした家制度、男性本位、結婚して子をなすのが正常な人、といったような発想が、残滓のようにこびりついている。
そんな中、墓や葬送のあり方にまつわる問題が、少子高齢化、経済格差などの「行き過ぎた資本主義」とも絡み合って、さまざまな形で噴出してきている。
あの墓はだれが守っていく(承継する)べきなのか、墓を購入するとはどういうことか、経営破綻も少なくないと言われるビル内墓苑にはどんな注意点があるのか、入れる予定の墓もない自分はどうなるのか、墓がなければ散骨で「処分」してしまっていいのか、男子がいない家系は墓を放逐することになるのか、同性カップルや内縁関係では、いざという時に何も手続きできない(死亡届すら出せない)のか、樹木葬や散骨とはどんなものなのか、孤独死した場合はどう扱われるのか、遺骨を移動したいが高齢で動けない、住職などに墓じまいや改葬を拒否される…。などなどじつにさまざまな問題が聞かれる。
いずれも簡単な問題ではない。また法整備は必ずしも時代に適合して行われているとは言えないし、具体的なシーンでは自治体によっても対応が異なることもあるようだ。
筆者は以前、ハワイでの海洋散骨の経験を踏まえ、現地の業者と協力して送客の仕事をしていた経験があるが、そのときもいろいろな話を聞いた。
しかし、死生観や宗教観のようなものは個人ごとに異なるものだし、家族や親族間で意見が分かれることもめずらしくない。そこには相続物件としての墓や祭祀道具、社会的責任のようなものが絡んできて非常に悩ましい。
さらには孤独死や孤立死などといわれる「ひとり死」で特に身寄りがない場合、自治体の負担で行われる葬送や埋葬は、今後増えていく可能性が十分にある。しかしだからといって、そのことを単純に批判したり問題視したりしても、何の解決にもならない。
本当は今すぐにでも本格的な議論を始めなければならないことなのに、ほとんど実効的な動きが見られないまま、今後も少子高齢化とひとり世帯が加速していく。
「昔のように戻ればいい」という論調もたまに見受けられるが、それはあまりにも非現実的だろう。
日本社会は、世界のトップを走る少子高齢大国だという。ならば、新しいものの考え方で、新しい制度設計が検討されるべきだろう。
明治以降のセンスで作られた法律や制度で組み立てられている日本社会では、想定されていない事態がすでに拡大し始めている。
繰り返しになるが、この問題は格差と貧困、性差別、家制度、LGBTQなど他のあらゆる社会問題とも絡んでいる。それはまた、人が生まれ、生活し、亡くなり、葬送するという一連の流れがよどんでいる状態だとも言える。
「これで解決」といった簡単な解はないだろうが、まずは多くの人がこういったことに対して問題意識を持つことから始めない限り、誰も幸せにはなれない国になっていく。
逆に、社会全体でこの問題に取り組むことができれば、関係する諸問題についても、一定の方向性を見出していくことが出来るかもしれない。
議論を活発化させることが難しいとしても、せめて何らかの提案をしている人、実際にその手の活動をしている人の意見に耳を傾ける努力をしたい。
やや大げさに言えば、そこからしか日本の未来を、子どもや若者たちの生きる社会を、希望的なものにしていくことはできないのではないか。
ビールと冷やしおろしそばをかき込む
ふたたび、管理センターと売店のある下まで降りてきた。
腹ごしらえをしようと「売店」をのぞいてみたが、お土産品としてのお菓子以外、食べるものといえばカップラーメンと給湯設備しかない。
困った。
慣れている人々はみな家から持参した弁当なり、コンビニめしなりを、テーブル席や座敷席で広げている。
園内地図を見ると、墓地公園の最上部にレストランがあるようだ。徒歩で標高差80mほどを登り下りしてきたところで、今また登るというのはツライ。
ちょうどやってきたオンデマンドのワゴン車があったので、頼んで乗せてもらう。本来は電話で管理センターに依頼し、指定場所で待つのがルールだが、空席があれば融通してくれるようだ。
ところがレストランに着いてみると、ウェイティングリストにズラリと名前が書かれている。待っている人たちは椅子に座っていたり、売店を見て回ったりしているが、このレストラン前を14時に出発する帰りのバスまで1時間もない。
それまでに食事を終えることができるかどうか…。いや、正直に言えば生ビールが飲みたくて仕方がない。
13時40分過ぎになって、ようやく席に着くことができた。冷やしおろしそばと生ビールの食券を券売機で購入し、席に着く。
猫型ロボットも配膳しているが、すぐに女性店員がやって来てくれ、手早く生ビールとそばを持ってきてくれる。
そばは濃い色の田舎そばのようで歯ごたえがしっかりしている。そこに桜エビのかき揚げを細かくしたものと大根おろしが乗っている。
急いでかきこみ、13時55分にバスに乗ることができた。
14時レストラン前発。
東京・浜松町へ向けて帰る東都観光のバスと合わせて5台、墓地公園内の中央の道路を下りていく。 途中の広場や、さらに下の管理センターに近いバス停でも、帰路のバスに乗ることができる。ほとんどの人はやはり、管理センター近くのバス停で待っていた。
新東名の新富士ICから横浜へと戻るが、足柄スマートICあたりから渋滞。そのため予定していた海老名SAではなく、手前の中井PAに入っての休憩となる。これは旅客自動車の運転手の、連続運転時間の制約とも関係している。
しかし、海老名SAのように広くない中井PAは、駐車車両でギッシリだ。
どうにかこうにか、ゼブラゾーンのスペースにバスを差し込むように駐めることができた。他のバスも違うところに何とか駐められたようだ。無線で連絡し合っている。
横浜町田ICから先は順調に走ることができたが、横浜駅の東口に着いたころには日も落ち、道ゆく人の顔も薄暗くてわからないような状況だ。
駅ビルの店先あたりで、甘ったるいナッツ系の菓子の香りが鼻に入ってきた。経済合理主義の現実世界に引き戻されたような気がした。
関連リンク
- アクセス情報(創価学会富士桜自然墓地公園)
- 富士急トラベル(東京・横浜発)
- 名鉄観光バス(2025年度名古屋発/PDF資料)
- 「おひとりさま時代の死に方」(井上治代著/講談社)
- 「みんな、本当はおひとりさま」(久本雅美著/幻冬舎)