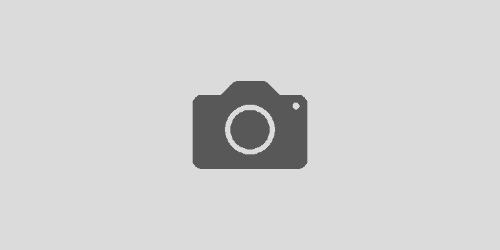秋の「タクシー激減日」

今年も「タクシー激減日」がやってくるかもしれない。
それは2025年10月24日(金)である。なぜそうなるのか。それは、車いすに乗ったまま、スムーズにタクシーに乗降できるかどうか、障がい者団体の呼びかけで全国一斉に実地調査が行われる日であり、非難やトラブルを恐れる乗務員たちが出庫を見合わせがちになるためだ。
タクシー会社の現場でもトラブルを避けるため、敢えて出勤を促さない傾向もあると聞く。
筆者は以前から関連する問題点を指摘してきたが、ハードウェアの改善が進んでいることは間違いない。しかしいまだに現場担当者、すなわちタクシー乗務員への眼差しが決定的に不足している。
そしてこうした問題は、医療・介護・教育の分野に横たわっている、本質的な問題でもある。
10年ほど養母と実母(いずれもすでに他界)を介護し、現在もタクシーのヘビーユーザーである筆者が、人のケアとその技術のあり方について考える。
※ 車いすの足元の画像は、生成AIによるものです。
INDEX
- 10月24日は事前予約がベター
- ジャパンタクシーの問題整理
- アクロバティックな車いす乗降
- ハードウェアだけ整備しても
- タクシー乗務員という特殊性
- 誰のための「技術」か
- 関連リンク
10月24日は事前予約がベター
まず冒頭、車いす乗車をしない一般の方にとっても大事なことを述べておく。
もし10月24日にタクシーを利用する予定があるのなら、事前に予約しておく方が間違いない。
予約は各種の配車アプリでもできるし、これまでどおり電話でも問題ない。
都市部の場合なら、大手グループが案内している専用電話番号にかけるほうがいい。そのグループの加盟会社、あるいは業務提携している多くのタクシー会社を対象にできるからだ。
10月24日が迫って来るにつれ、予約が難しくなる可能性も考えられる。できれば早い方がベターだろう。
また、車いす乗降に関する「全国一斉調査」は、いちおう10月中を通して行われるようなので、留意しておいた方が無難だ。
なお、当然ながら指定場所にタクシーを呼べば「
さらに、アプリでタクシーを呼んでおきながら、アプリ事業者が推奨する決済方法をとらない場合(車内で現金払い、またはその他キャッシュレス決済)は、「取扱手数料」などといった名目で、さらに加算される場合もある。
ちなみにスマホやタブレットで迎車位置(タクシーに来てもらいたい地点)を指定する場合、地図上の希望地点をタップして設定するのだそうだが(筆者はアプリを使っていない)、地図をなるべく拡大して厳密に指定しないと、間違った場所にタクシーが向かってしまい、予定通り乗れないことがあるので注意しよう。
「マンションの建物が指定されていたので車寄せで待っていたら、お客さんは裏口で待っていた」、「隅田川の真ん中に迎車ポイントが指定されていて困った」、「待てるような場所、交通状況じゃないところに呼ばれ、トラブルになった」などという話を、タクシー乗務員からよく聞く。
配車アプリを利用する側にも、一定の情報リテラシーと、状況判断力(というか常識的感覚)が求められそうだ。
ジャパンタクシーの問題整理
トヨタ社製の「ジャパンタクシー(以下「JPN TAXI」と表記)」は、車いすのままでも乗れるタクシー専用車両だ。
発売は8年前となる、2017年秋。
「次の日本に、いらっしゃいませ。」というキャッチコピーも秀逸で、令和の東京オリンピックを控えてタクシー業界はもちろん、車いす利用者やその家族、医療・介護関係者の期待と関心が盛り上がった。
JPN-TAXIは本体価格が高額となるため、導入するタクシー会社に対しては、国の補助も投入されたという。
しかしその実態は、(おもに車両構造・設備に関する)約1万2千名の改善要望の署名が集まったり、トヨタの設計担当者も「甘かった」と認めたりするほどで、障がい者団体をはじめ、多方面から疑問の声が上がる事態となった。
ジャパンタクシーの問題点は、「(介助者がいる、いないにかかわらず)車いすの人が利用しづらい」ということである。
具体的には、「乗車拒否される」、「乗降に要する時間が長すぎる」、「乗務員が大変そうで頼みづらい」といった点である。
「車いすのまま乗れるタクシー」と鳴り物入りで登場した割には、発売から8年が経過した今も、現実にはほとんどその
アクロバティックな車いす乗降
なぜこうなってしまうのか。
筆者は、「車両の企画・開発担当者や、業界の経営・管理層に、現場担当者への眼差しが決定的に欠けている」という点を指摘したい。
さらに言えば、こういった問題は医療・介護・教育といった分野に横たわる、根本的な社会問題であるとも考えている。
JPN-TAXIの場合、LPガスとバッテリーのハイブリッドとしたため、大きなガスタンクを、後席とラゲッジスペースの間に配置せざるを得なくなった。
そのため、車いすを車両後部からスロープで乗降させることが不可能となり、左側(歩道側)から乗降させるという、アクロバティックな設計をせざるを得なくなる。
そうして、①折り畳み式スロープの組み立てと分解収納、②車内での車いす90度回転、といった2大作業が必要となる。
さらに、これらに付随する作業がいくつもあり、そのために使用する器具も多い。
たしかに、車両のマイナーチェンジのタイミングで、車いす乗降に関するハードウェア設計は見直されてきてはいる。
しかし、それは枝葉末節レベルの改善でしかない。
ハードウェアだけ整備しても
JPN-TAXIの車いす乗降が非現実的である理由は、こうしたハードウェアの問題に限らない。
乗車と降車の2度、こうした作業をするのは乗務員(タクシー運転手)である。
しかし、一定の練習をしているであろう乗務員も、めったに発生しない車いす乗降の複雑な手順や、そのコツを忘れてしまっている場合が多い。
また、必要な器具の点数も多く、紛失してしまっている場合もあるようだ。
動画サイトなどには「お手本ビデオ」のようなものが多く上げられているが、そこに登場しているのは、比較的スリムな体格で機敏に動ける人物である。
しかし現実には高齢の乗務員も多いし、「重量感」のある乗務員、逆に小柄で
例えば、こうした個々に事情を抱える可能性がある現場の「人」という存在を、一概に標準化して考えてしまう思考の雑さは、いかにも「昭和的」といった感じがする。
タクシー乗務員(現場担当者)は、事情もクセもわからない乗客(サービス利用者)と、規格化されたハードウェアを前に、自己犠牲的な働き方を要求されている。
タクシー乗務員という特殊性
(個人タクシーではない)会社勤めのタクシー乗務員に限っていえば、その収入はメーターの売上の一定割合となる。
実際には会社ごとに細かい算定基準があるが、いわゆる「頑張った分だけ収入に反映される」という歩合制の仕事に他ならない。
そのいっぽうで、旅客自動車の運転手である以上、その運転時間や休憩時間、勤務間隔などが厳しく管理されている(違反の程度によっては乗務員資格の停止や剥奪があるという)。
こうした「制限時間内の歩合給」といった労働環境で、収入の最大化を図ろうとするとどうなるか。やはり時間あたりの売上高、すなわち時間効率を上げるしかない。
言い換えれば、「時間ばかりかかって売上につながらない作業」は、この仕事においては決定的に忌避すべきこととなる。
事故やトラブルも含めてメンドウなことが起きた時、彼らにとって何より大事なことは、「さっさと片付けて、次の客を乗せる」ことである。
こういった面からも、車いす乗降のサポートにモチベーションが働きにくく、いわば「自己犠牲的精神の発揚」を周囲から強要されているのが実態だ。
それゆえ、「車いすの客にアタッてしまった!」という言い方になってしまう。
タクシー乗務員を批判したり懲罰を加えたりすることは簡単だが、そもそもの構造的問題や事情は、そういう態度をとる人々の視界には入っていない。
そしてこういった傾向は、医療・介護・教育に携わる人々を安易に批判するときの思考パターンでもある。
バスや電車なども同じことだが、そもそも乗務員(ここでは運転・操縦担当者)という人々は、いわば機械オペレーターである。
個々の乗客扱いでサービス精神を発揮したところで、彼ら自身にメリットは何もない。それどころか、そのことに起因して事故やトラブルに発展すれば、叱責や懲罰を受けてしまうという、ゆがんだ立場に置かれている。
誰のための「技術」か
JPN-TAXIそのものは評価されるべきである。
しかし、そのせっかくの技術も、誰かの犠牲の上に運用されているのだとすれば、そしてそのことが意識されていない社会なのだとすれば、果たしてそれは持続可能なものと言えるだろうか。
車いすのままタクシーに乗れることは素晴らしいことだが、表面的な部分だけを見て議論していても、問題の本質に迫ることは出来ない。
話を広げるが、医療・介護・教育といった、人が人をケアする現場はみな同じではないか。
現場を支える「人」へのまなざし無き技術運用、理論展開は、ケアされる人のことを考えているのではなく、誰かの影響力の最大化を目的としているようにしか思えない。
「私たちは、地球と子どもの未来のために貢献しています」的なことを謳いながら、じつは誰かの犠牲のうえに成り立っている構造には意識を向けようとしない。
そうだとすれば、その考え方こそ、これからの日本にとって最大の障害ではないのか。
そもそも「技術」というものは、チャレンジと改善の繰り返しである。
そのチャレンジと改善のプロセスで、ケアする人へのまなざしが忘れられていないか、我々は考え直すべきである。
そうしなければ、持続可能な社会の実現はもちろん、かつて見下していた国々以下に沈んでしまっている現在の国際的地位も、二度と浮上することはないだろう。
関連情報・リンク
- 筆者過去記事
- 車いすのままタクシーに乗る人の意見(2023年10月23日、筆者)
- 10月20日、タクシーが激減する?(2023年10月3日、筆者)
- タクシー東京大手四社(大日本帝国)
- おもなタクシー配車アプリ