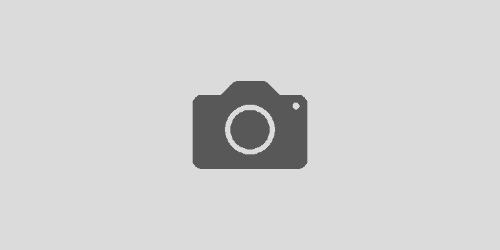遠くにある大阪万博

夜勤明けの土曜日、数時間ウトウトしたあとテレビをつけてみると、大阪万博の開会式の様子を中継している。ちょうど実力派音楽デュオが歌っているところだ。
天皇陛下や内閣総理大臣をはじめ重要人物が集い、おそらくかなりの練習を積んできたのであろう若者や子どもたちによる、質のいいパフォーマンスやビデオ・コンテンツが披露されている。
しかし筆者は、見れば見るほど虚しさを感じてしまう。
あいさつに立った開催地の知事の表情にも、「思い描いていたのとはずいぶん違ってんだけど…」といった気持ちが滲んでいるようにさえ見えた。
INDEX
- 不思議な置き去り感
- シャンパン・タワー思考
- 数値化できない世界で
- 考えさせない、それが一番大事
不思議な置き去り感
冷静に考えれば、天皇皇后両陛下、皇位継承順位第1位の秋篠宮文仁親王・同妃、内閣総理大臣が、時と場所を同じくしているということの意味は大きい。国家レベルで力を入れていることの証左であるといえる。
しかし、なぜか開会式が虚しい。置き去りにされているような感覚と同時に、一部の人々だけが勝手に盛り上がっているという感想を持ってしまう。
世間ではよく、未完成のパビリオン(展示館)や前売りチケットの販売不振などが槍玉に挙げられる。
しかし筆者としては、「遠くの方でみんなが集まって楽しそうにやっているけれど、その時空にはたぶん到達できないであろう自分」、あるいは「盛り上がっている人々の意識には存在していないのであろう階層の自分」、そんな構図を突きつけられているような感覚すら持ってしまった。
そもそも「万博」という言葉そのものが、なにやら前時代的な響きを持っている。特に我々の世代の場合、1970年(昭和45年)の大阪万博を想起し、並べて考えてしまうからか。
筆者はその当時、石川県金沢市の団地で、両親そして兄二人とともに暮らす5歳児だった(長兄はすでに名古屋へ働きに出ており、筆者にとってはたまにやってくる知らないお兄さんであった)。
そして「当家からは」中学生の兄が、まるで家族代表としての決意を胸にするようにして、大阪万博へ出かけて行った。
もちろんそれは個人的に計画して行ったのではない。修学旅行の目玉として組み入れられていた見学であった。
当時は個人の立場で「汽車賃」を払ってまで大阪へ出かけること自体、筆者の家としては歴史的出来事というべきである(すでに485系特急電車は活躍していたが、一般には「汽車・汽車賃」と言い習わしていた)。
その中学生の兄に、修学旅行積立金などで恥をかかせないようにと、両親が必死で働いていた姿も思い出す。
修学旅行、いや大阪万博へ出かけるこの家の中学生の息子には、家族の期待と羨望のまなざしが集まっていた。
これは簡単に言ってしまえば、日本社会全体が上昇気流に乗った、高度経済成長期であったということになるのだろう。そのころ5歳児であった筆者でも、自分たちの家が周囲と比べて経済的に貧しいことは、日常のいろんなシーンで感じ取っていたけれど、生活全体の中で悲しさや虚しさはあまりなかった。一瞬は悲しくても、じきに解消されていた。
シャンパン・タワー思考
「経済的勝利者の祝祭」とでも言うものを表す典型に、シャンパン・タワーというものがある。シャンパン・グラスをテーブル上に山のように積み上げ、一番上からシャンパンを注ぐ。やがてあふれた液体は下へ下へと広がっていく。
筆者などは下品な小金持ちの所業にしか見えないのだけれど、このシャンパン・タワーのようなものが、国家の経済政策を説明する文脈で使われることがある。
つまり国家が、より直接的に関与しやすい大企業などへ措置を講ずれば、やがてはそれが社会全体へと波及していくのだという考え方だ。
これは確かに一理あるけれども、これには一定の時間がかかる。その時間が経過しているうちに、すなわちシャンパンが最下層に届く前に、社会も世界も変化していく。
新しい社会状況に対応して、また新たな施策が実行されるのだけれど、こうした時間差が積み重なり、いつまでたっても下層は下層のままで固定化されていく。そんなことが繰り返されてきたのが、この国の「昭和100年間」の一面だったようにも思える。
そしてその考え方で走ってきた結果が、最もわかりやすく現出している部分こそ、教育・介護・医療の世界ではないだろうか。
こういった世界で働く人々のパフォーマンスは、単純に数値化できない。しかし、我々が「人間」であるという根本的な部分で、欠くことができない最重要な部分である。
数値化できない世界で
こういった文脈で、たとえば「教育」という言葉について考えてみよう。
「教育」と聞くと多くの人は、学校などの教育機関によって行われる集合教育をイメージするかもしれない。
すなわち個人の「学歴」というところに記録されるものであり、個人が(とくに初期段階で)社会に判定・選別される際の基礎データともいえる。
そして多額の金が必要とされる「よりよい教育」を受ける事が出来ない家庭の子どもたちは、親の世代になっても経済力を高めることが出来ず、これが次世代へと続いて固定化していく、という考え方が一般的な理解となっている。
もちろん、これも重要な問題意識だ。
ただ筆者は、これにくわえて「家庭教育」と「社会教育」にも意識を向けなければ、この問題を正しくとらえることはできないと考えている。
たとえば「ケーザイってなぁに?」と小学生の子どもが、あるいは「経済って、要するに何なん?」と中学生が、最も信頼する大人すなわち親に問いかけた時、その親はどのように説明するだろうか。
同じことを説明するにも、ある程度「経済学的」なものを理解している親と、そうでない親とでは、説明にも格段の違いが出てくる。
「まじめに勉強して学歴つけとかないと、大人になってから苦労するぞ。つべこべ言ってねぇで勉強しろ」みたいなことしか言えないとすれば、その子どもは、家庭とは別の場でのいい出会いがない限り、社会というものを、自分が参加したり意見を述べたりすることのできないものとして認識し、投票しない、考えもしない有権者になっていく。そしてその人生において「いくら稼げるのか」といった経済活動にしか意識を向けることができない、いわば「飼われた国民」となっていく。
しかしこれは、既得権益者や為政者にとっては好都合な社会だ。
問題意識を持ち、正しい言葉で、論理的に、正しい手法をもって社会に働きかけていく。そんなことができない国民の方が、コントロールは容易である。
狭い視界の中で、短期思考しかできないようにしておけば、その都度「エサ」を撒いておけば、静かにさせておくことができる。
あぁ、なんて日本は平和な国なんだ。
くわえて、「数値化できないものは考えない」、「言語化・理論化できないものは認めない」、そんな考え方が過度に社会を覆っていくと、我々は自分で自分の首を絞めていくことになるのではないか。
考えさせない、それが一番大事
「政治改革」「政治とカネ」「汚職」「日米地位協定」こういったキーワードは、筆者も幼いころから「慣れ親しんでいる」。
もっと正確に言えば、この国では敗戦後100年間にわたって、こういったキーワードが叫び続けられながら、けっきょく根本的なところは何ら変わってはいないということだ。
そしてここ数十年には「議員定数削減」「格差」「差別」といったキーワードも追加されてきた。
これからも我々は、ずっとこれらのキーワードを叫びながら、相も変わらず政治家たちや各界をコントロールする者たちによる「目くらまし」を受けつつ、この国は進んでいく(あるいは崩壊していく?)のだろうか。
もしそれがイヤだというのなら、我々自身が気づかねばならない。 いまの社会状況は、経済活動だけに目を向けさせられてきた戦後の日本人が、少なからず「選択した」、あるいは「選択させられてきた」結果だということだ。
筆者はこれまでのブログ投稿の中でときどき、日本社会に欠けているものとして、「宗教に関する正しい教育」を訴えてきている。それは、サルではない我々人間に当然必要な思考力であり哲学であるといえる。
そこを雑にタブー視し、アンタッチャブルにしてきたのが戦後の日本社会であり、その結果、「社会の中で正しく機能している宗教」と「宗教に名を借りた単なるテロ・殺人集団」の区別もできない国民になってしまった。
数値化することでしか現実社会を測ることが出来ず、数値的・論理的対策さえ実行すれば社会はうまくいく、といった偏った思考から脱却できない限り、次の百年もわれわれ日本人は、その精神的な部分での成長は見込めないのではないか。
「(待ち行列に)並ばない万博」が、うまく運んでいないという。
その原因は、理屈でしかものごとを考えられない管理者たちと、現場で実際に生身の人間と向き合っている人々との、「世の中の見え方」の違いによるものではないかとも考えている。
天皇陛下の御言葉の中で、
「『大阪・関西万博』を契機として、世界の人々が、自分自身だけでなく、周りの人々の『いのち』や、自然界の中で生かされている様々な『いのち』も尊重して、持続する未来を共に創り上げていくことを希望します。」
という部分があった。
このフレーズが、日本の政治家たちや、あらゆる組織における管理者たちに向けられた、痛烈な指摘に聞こえたのは、筆者だけだろうか。