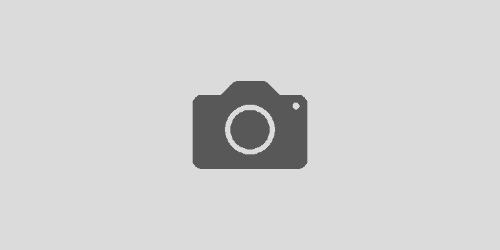オウム・統一教会、日本に欠落しているもの

旧・オウム真理教が関わった一連の重大事件とその周辺を考えるにあたり、いまだに忘れられている問題、あるいは意図的に避けられている問題があることに気づく。それは、「社会の中で正常に機能している宗教と、宗教を騙った単なる殺人・テロ集団との違いが説明されていない」ということだ。われわれ日本人がここを真剣にとらえなおす努力をしないのであれば、今後もまた似たような事が起きる可能性がある。
INDEX
- サル的人間
- サルはイメージが出来ない
- 科学と宗教(1)
- 科学と宗教(2)
- 見極める力
- 日本社会に欠落しているもの
- 都合のいい社会
サル的人間
多くの日本人が宗教というものを意識する機会は、おそらく2種類ではないだろうか。
そのひとつは、冠婚葬祭である。これらは個人の人生の節目、あるいはその社会の節目であり、いずれも時間の流れの中で意識する機会ともいえる。
そしてもうひとつ宗教を意識する機会は「事件」ではないだろうか。
ある宗教団体が反社会的なことをやっていた、そしてそれは現在も継続している、といったマスメディアやSNSの情報である。
「幼い時は神社にお参りし、結婚式はキリスト教式で挙げ、亡くなった時は仏教の習慣にしたがう」などと揶揄される日本人。そんな浅薄な宗教観しか持ちあわせない日本人は、その根底的な部分において世界の人々から信用されていないなどと言われる。
多くの日本人にみられる宗教に対する感覚は、たとえば「宗教は各種の儀式や行事に必要なものかもしれない。しかしそれはツールでしかない。そしてツールだけに、悪意をもって利用されればとんでもない結果を招く」とか、「一定の距離を置いておくべきで、まじめに関わったら自分も家族も身を亡ぼす、恐ろしいもの」といったところだろうか。
しかし、こういった状況は国際的に、
「つまり日本人には確固とした宗教観がない。それは人生哲学を持ち合わせていないサルということだ」
「経済協力の引き出しと、国際問題発生時のクッション材としての利用価値しかない小賢しいサル」
とでもいう、見下すような深層意識につながっている。
(参考)
ここでいう「サル」をより厳密にいうとすれば、巨大な大脳を持つ我々「ホモ・サピエンス・サピエンス」をのぞいた、ヒト科一般(チンパンジー、オランウータン、ゴリラなど)を想定している。しかし生物の分類というものもなかなか難しいらしく、スッパリと分類できない面もあるようだ。
サルはイメージが出来ない
「人間とサルは何が違うでしょう?」
そう問いかけられれば、いくつか挙げられるかと思う。
本稿では、「サルは自分の目で見えるもの、あるいは自分の手などで感じられるものからしか、思考を始めることができない」という前提に立つこととする。
たとえば我々は、紙幣や硬貨などを大切なものとして取り扱う。その紙きれや金属を価値あるものとして認識でき、溜め(貯め)こんでみたりする。
しかしサルはそんなことはしない。彼らの脳では、紙幣や硬貨という物体に、「食い物ほか、いろんなものにも交換でき、その価値は比較的長期にわたって保証されており、また他人に貸してやれば増えたりもする」などという「物語」をそれに乗せることが出来ないからだ。
また同様にサルは、比較的大規模な共同体・組織を構成することもできない。せいぜいボス猿を頂点としたグループを作ることが出来るくらいで、それ以上の規模の組織は作ることが出来ない。
なぜなら、たとえば会社などといった組織は、自分の目や耳で認識できる範囲、自分の手足でコントロールできる範囲を超えているためだ。
ましてや国家などという大規模組織を構成・運営することなど不可能である。
しかし人間は、自分の目や耳で認識できなくとも、自分の手足でコントロールできなくとも、会社や国家という共同体を運営していくことができる。この先の未来に起こりうる事態をイメージできるがゆえである。
こういった「目に見えない、手にとって触ることもできない物事」をイメージしつつ大規模な組織を構成・運営する能力は、人間の人間たる特徴といってもいいだろう。
しかしその卓越した能力は同時に、「悩み」や「疑問」をもたらすことにもなった。すなわち、「(自分のことであれ他の人のことであれ)人は死んだらどうなるのか」、「死んだ後はどんな世界が待っているのか」という問題である。
科学と宗教(1)
「科学的に証明されたものなら真実だが、宗教などというものは気休め、あるいは人を惑わせるいかがわしいものだ」という対立的な整理をしている人も多い。しかし、この考え方は大きな矛盾を孕んでいる。
科学も宗教も、人間にとって「わからないもの」に対する探求の歴史であり、そのアプローチが異なっているだけだからだ。
「そんなこと言ったって、科学なら実験をしてみれば、どこでも誰でも再現性を確認できる。答えはハッキリしているのではないか」というかもしれない。しかしこれは、思考の時間的スパンがあまりに短すぎる。
我々が「いわゆる科学的思考」をするようになったのは、歴史的に見てごく最近の事である。それにくらべて宗教的思考はとてつもなく長い歴史、すなわち「民族レベル、人類レベルの経験則」とでもいう実績を持っている。
たとえば宗教の中には、食物タブーというものを持つものがある。よく調べてみるとこれらは、じつは経験則にもとづく科学的思考という面が確認できる。
つまり(その当時の)衛生上の問題であったり、効率的な農耕に欠かすことのできない動物を減らさないための知恵であったりするという、科学的な理由がその根底にある。
そして、それを当時の人々に納得させるために、神という超越的存在と絡めて人々に教え諭した、と考えることができるのだ。
神がいるかどうかは別としても、結果として科学的・合理的な生活態度を採用していると言えないだろうか。
細菌がどうの、ウイルスがどうのなんてさっぱり知らないけれど、牛を食べつくした人々は農業生産力を落としてしまい、やがて餓死して滅んだとか、不衛生に飼育されていた動物や野生動物を食したため多くの人が死んだ、などといった長期的な経験から、「これをするとヤバイことになる」と学んで伝承しているわけである。
逆に言えば、衛生的なものを食べるようにするとか、牛という労働力を大切にするとかしていれば、自分たちは将来も困らないということを学んで実践していることになる。
ただ後年、その表面的な戒律のみが生活様式として残り、本来の「より幸せに生きるための行い」という目的から離れてしまい、形式主義的・権威主義的になっている部分はありそうだ。
ところで、ネアンデルタール人の骨が見つかった遺跡では、その骨とともにたくさんの植物の種子も発見されているという。
これは亡くなった仲間に花を供えて「葬った」証拠であると考えられ、そのころから死というものへの抽象的思考が芽生え、宗教的な思考をする程度にまで脳が発達していたのではないかと考えられている。
(参考)
ネアンデルタール人はすでに絶滅しているとされる。また現在、ネアンデルタール人は我々の直系の先祖ではなく、別系統の人類に属するという考え方が有力らしい。ただ、われわれ現生人類のゲノムには、ネアンデルタール人の遺伝子が数パーセント混入しているとの説もある。
科学と宗教(2)
「死後の世界なんてあるわけない。死ねば脳の活動は停止するわけで、つまり夢を見ないで寝ているようなものだ。なんにもありゃしない。」という主張がある。
いっぽう多くの宗教ではしばしば、「あの世」もしくは「生まれ変わった次のステージ」でのありようは、「この世」での行いが影響するのだ、といったことが語られる。つまり魂とでもいうような「自分的な存在」が継続していくのだという考え方がある。
そこで「死んだら何にもありゃしない」という人々は、「そりゃぁ現実社会をよりよく運営するための、有効で意味のある物語なのだ」と説明したりする。
そもそも人間は、「自分は確かにこの世に生きている。他の人間と共感しあったり反発し合ったりしながら生き、そうしていつの日か死ぬのだ」と知っている。
じっさいに自分の周囲で人は死んでいくし、自分にとって大切な人が亡くなればとてつもなく落ち込む。
自分が生き残る側であれ、死にゆく側であれ、いつか必ずそうなることは明々白々に理解できている。
ということは、少なくとも「生きている」という状態と「生きていない=死んでいる」という異なる状態が存在するということについては認めているということになる。
しかし、こうして「なんだかんだ」と考えているのも、けっきょくは自分の脳である。脳ではいろんな物質が作用を起こしていたり、あるいは電気信号が走っていたりして、目・耳・口・鼻・触覚などから入ってくる電気信号を「処理」しているのだという。
何の話だったか忘れたが、横たわっている人間の頭に特別な機械を被せて脳をコントロールし、「自分という存在として生きている」と認識させる話を聞いたことがある。
横たわっている人はその脳の中で、寝たり起きたり仕事に行ったり、喜んだり悲しんだりして、その「特殊な装置によって生成された自己」を生きるというSFだ。
こんなことが技術的あるいは倫理的に実現できるかどうかは別にして、この話が提示していることは「現実と思っていることも自分の存在も、ましてや『あの世』も、つまりは脳内物語なのであり、命も意識も含めて存在という存在はすべて、ある種の幻影といえるのではないか」ということかもしれない。
この考え方を推し進めていくと、「人生に意味なんてない」「自分探しをしたって、どこにも存在しやしない」という考え方になっていく気もする。
だけれども…、と筆者は考える。
「この世」も「あの世」も含めて、すべての存在を存在として認識し、意識する(してしまう)のが人間という生き物であることは「人間にとって事実」なのであり、サルとは異なる脳を持つに至ったホモ・サピエンス・サピエンスの自然なありようであると考える。
すなわち我々が現実に生きている(と思っている)この人間社会や自然環境が、たとえ壮大なる脳内物語であったとしても、そう認識している脳こそが人間存在であるとでも言おうか。
そうだとすれば、楽しいと感じることは大きくしたいし、悲しいと感じることは癒せるようにしたいと考えるのが自然だ。
さらに社会とかかわって生きることが人間と呼べる要件なのだとすれば、社会的存在としての自分を成長させ、あらゆる形で他者を支えられるような自分に変わっていきたいと願うのが、人間の自然なありようというものではないかと思うのだ。
そういう意味において、人間に示唆を与えてくれるものが(あるいは物語が)宗教なのだと考えれば、少しは宗教というものの見え方が違ってくるかもしれない。
見極める力
国家転覆を意図したテロ行為(地下鉄サリン事件)も含め、数々の重大な犯罪や反社会的行為を実行してきた人間集団が、旧・オウム真理教であった。
その集団は当然ながら宗教法人格を剥奪され、その後に組織を変更し、名称を変更したが、その反社会的態度につながっていく根本的な思想は、連綿として継続していると考えられている。
またこれとは別に旧・統一教会も、反社会的実態(霊感商法)、反国家的な組織システム(他国への国富の流出、政権との癒着)が疑われるとして、現在も裁判の場を含めて大きな社会問題として関心を集め、人々に注視・警戒されている。
いっぽう、これらの例とは逆に、「あやしい」と騒がれたものの、なにも問題はなかった例もある。
忘れている人も多いと思うが、そのむかし「イエスの方舟」と呼ばれる集団が存在した。その名の通りキリスト教をベースにした思想を持っていたようだが、主宰者の男性が複数の女性と共同生活していたことが取り上げられ、ほとんどのマスコミが今でいう「バッシング報道」を展開した。
けっきょくその男性は出頭したものの逮捕されるようなことはなく(逮捕するべき事実はなかったということになる)、その集団の実態が少しずつ明らかになっていくと、バッシング報道は収まっていった。
このときの一件がトラウマとなったのか、その後に起きたオウム真理教に対するマスコミの報道が、このバッシング事件によってやや及び腰になっていたのではないかという指摘もある。
また、ジャーナリズムとは言い難い活動を展開する人たちがよく取り上げて攻撃するのが創価学会である。
周知のとおり自民党とともに現在、政権与党におさまっている公明党は、創価学会(1952年に宗教法人の認証を取得)が支持母体である。つまり宗教団体が政党を結成し、政治活動を行っているわけだ。さて、これは「問題」だろうか。
もしも、「問題だ。政教分離に反しており、憲法違反だ。証人喚問だ。」などと考えるとすれば、重大な勘違いである。しかしそう主張して熱心に活動していた人たちが現実に存在した。何のことはない、「政教分離」の意味を知らないだけであった。
「政教分離」は、政治権力側(すなわち日本政府)が特定の宗教を優遇したり、逆にそれ以外の宗教を制限したりするようなことを禁止するものだ。けっして宗教的信条をベースにして政治活動を行うことを禁じているものではない。つまり権力側を縛るための「一方向」の規定なのである。
これは本来、中学生レベルの理解なのだけれど、ジャーナリストを自称する者、大学教授、国会議員などにも、そうした人物が存在していたのである。
日本社会に欠落しているもの
先述した旧・統一教会は現在、「政府のやっていることは自由な宗教活動を妨害するものであって、政教分離原則に反している」というようなことを主張している。
もしそれが事実なら、日本は近代国家として重大な問題を抱えていることになる。
ここで考えなければならないことは、それが「認められるべき自由な宗教活動」なのか、それとも「反社会的活動、犯罪として立件される行為、あるいはそうした状態を助長したり、黙認したりしている」のかどうかという点ではないだろうか。
ただし、こういった問題を考えたり議論したりするためには、前提となるそれなりの知識が必要になってくる。それは「宗教活動とは何か」であり、「宗教とは何か」ということにもつながっていく。
ところが日本社会では戦後、宗教に関する教育や学習が公的には行われていない。当然ながら、国家が宗教教育をしてはならないとされているからだ(日本国憲法第二十条、および教育基本法第十五条)。
これは、戦前・戦中の「国家神道」と呼ばれる思想が悲惨な戦争を招いただけでなく、更にそれを徹底的に悪化させた反省があるからだが、これがまた大きく逆にブレてしまった。宗教そのものがヤバイ、という雑な考え方、空気になってしまい、経済的繁栄のみが人間を幸福にさせると考え、「生命哲学、人生哲学なきエコノミック・アニマル」として生きようとする社会を作ってきてしまった。
「何がいけなかったのか」を反省したり総括したりしないまま、ある意味、水に流して忘れようと努力して、経済社会の構築に突っ走ってきた結果でもある。
では、宗教教育なしで社会は平和にうまく回っていくのだろうか。
筆者はそうは考えない。「宗教に関する正しい教育」は平和な社会のためには必要だと考える。また平和であってこそ経済も発展する。
しかし、学校のようなシステマチックな集合教育を想定する限り、それは難しい。そこで、学校や会社といったような社会制度として作られている集団ではないところで、宗教に関する対話をすることが求められるのではないかと思う。
なにも難しい話をする必要はない。自分はこう考えている、ということを表明し合い、お互いに「ふーん」というレベルで納めておくだけで、まずは十分だと思う。
少し熱心にやりたいのなら、たとえば池上彰氏が書いているような宗教に関する本でも1冊買って感想を述べ合うのもいい。
本選びのポイントは、世界の歴史と人間社会というものを、社会学的な広い視野でとらえつつ異なる5つ程度以上の宗教を比較・解説しているものを選ぶことだ。この選択を誤ると、よからぬ方向へ「持って行かれてしまう」可能性も出てくる。
都合のいい社会
本稿の冒頭に述べた、「社会の中で正常に機能している宗教と、宗教を騙った単なる殺人・テロ集団との違いが説明されていない」という点は、優秀なプロフェッショナル集団であるはずのマスメディアにも、そうした理解が進んでいないことを証明している。
日本に欠落しているもの。
それは宗教について一般の我々が気軽に語り合うことだ。わからなければ、「わからない」と言えばいい。触れる事さえタブーであるような空気では、日本は宗教に無知で判断力を欠いた人間集団として、国際的に尊敬されることもないばかりか、ふたたび「宗教を騙った反社会的集団」の災禍を受けることにもなりかねない。
それを避けるためには、日本人一人ひとりが、精神的自立を遂げることが必要になってくる。それはたとえば「私はこう思う」と述べる姿勢だ。
いつまでも、「周囲に合わせて無難にやり過ごそう。波風を立てないのが一番だ」という考え方であっては、「宗教を騙った反社会的集団」にとって、都合のよい社会の再構築を繰り返すことになる。